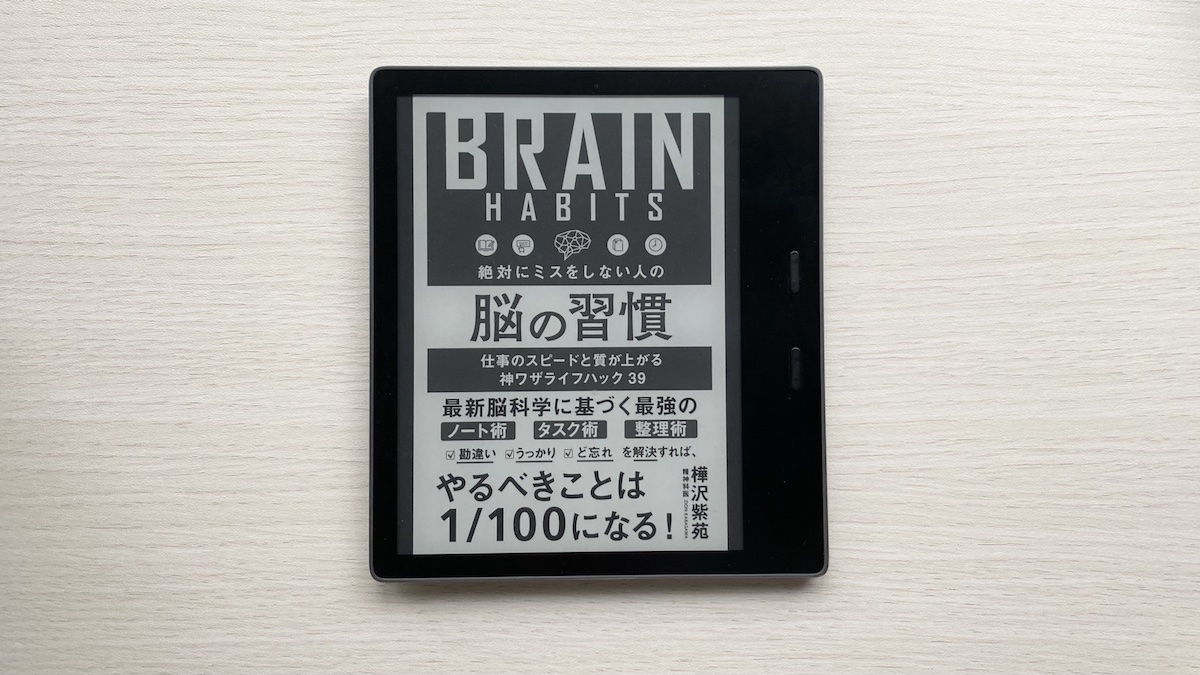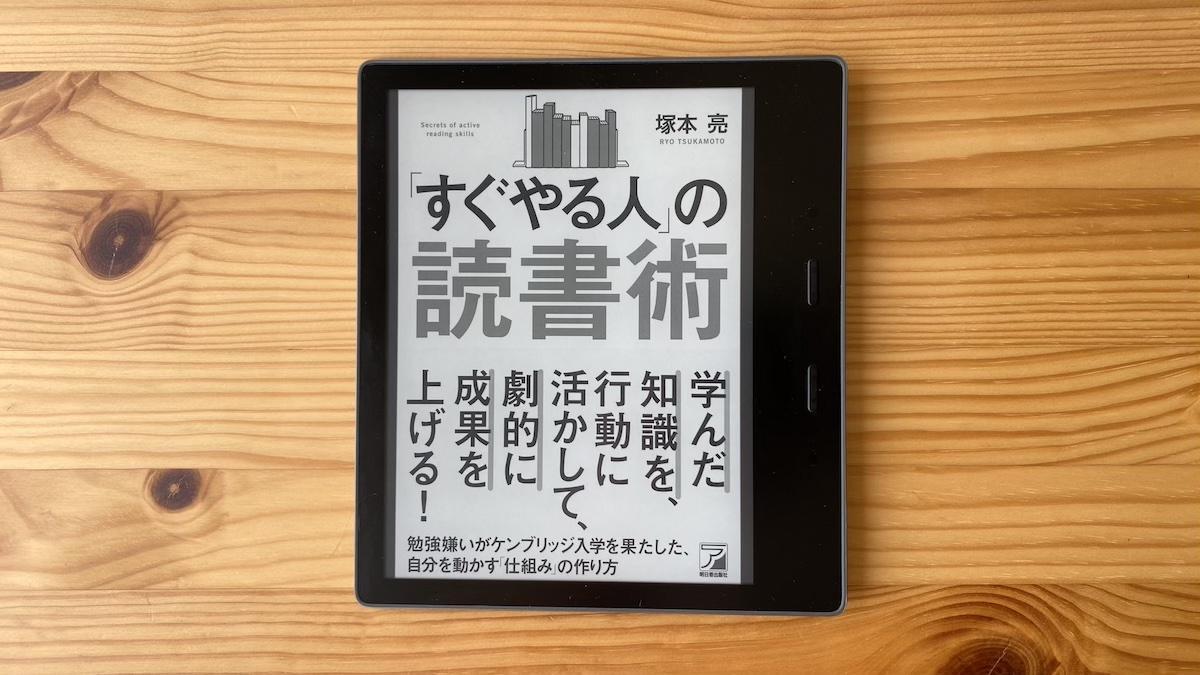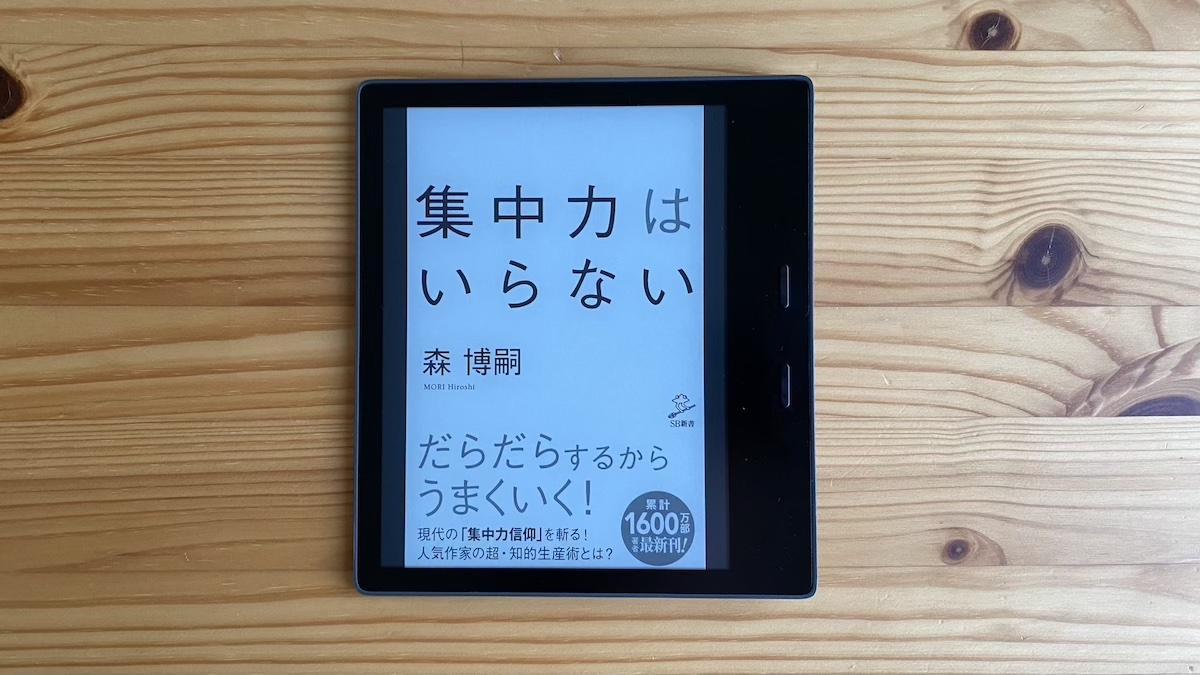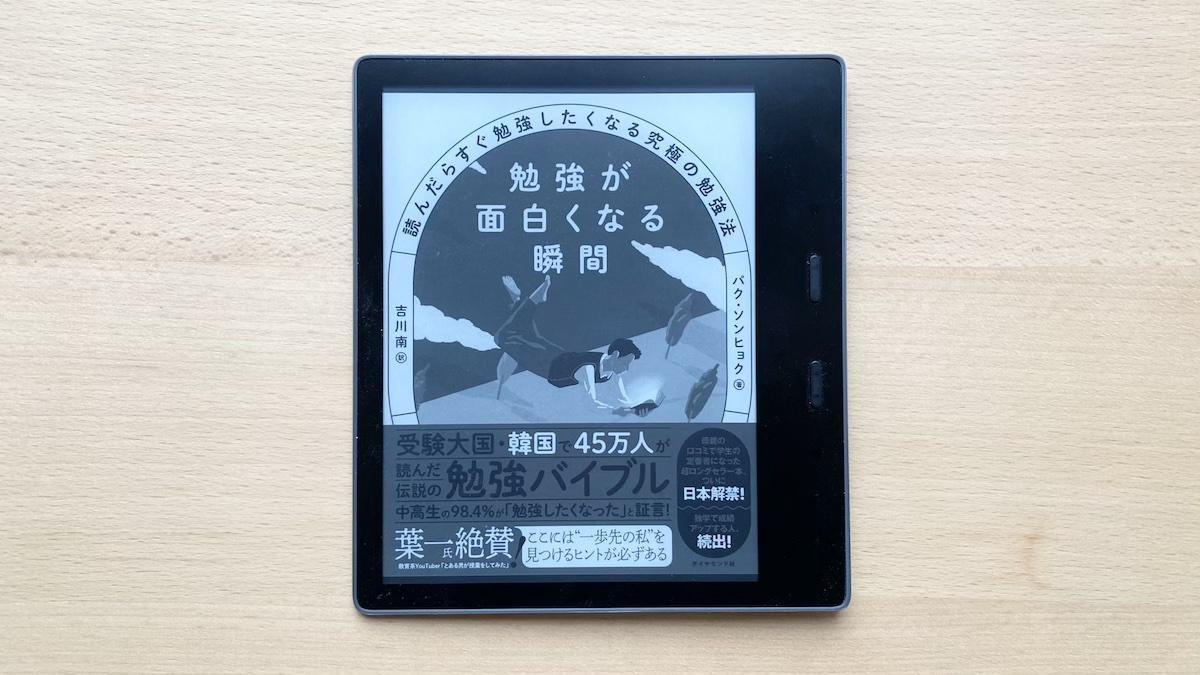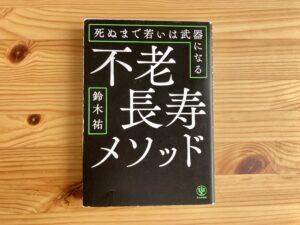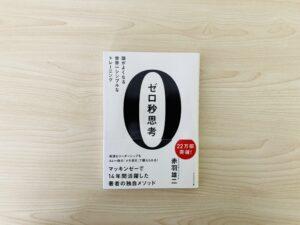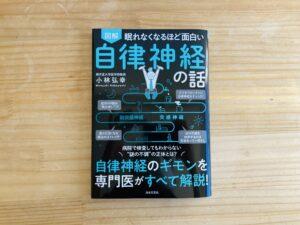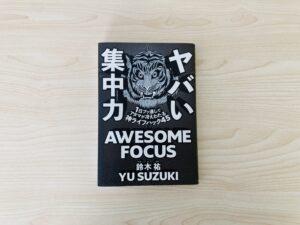ドレミの音階をつくったのはピタゴラスだという事実を知り、面白いなと思ってこの本を読んでみました。
「そもそも何でドレミとなっているのか?」
「音の定義ってどうやって決まったのか?」
っていう音楽の基本的な知識は音楽の時間に習わなかった気がします。(たぶん)
この本では数学の小難しい話も出てくるので、正直言っちゃうと興味のある部分しか読まなかったのですが、
この本がおすすめの人
- 数学が好き
- 音楽が好き
- 雑学・うんちくがすき
という方はぜひ読んでみましょう!
ドレミはイタリア語だった
ドレミファソラシドって、そもそも何語だと思いますか?
ドレミは実はイタリア語だそうです。日本でも一般的な言い方ですね。 ちなみに日本語とハニホヘトイロハですね。
誰が決めた?
じゃあ誰が決めたんですか?ということですが、10世期後半のイタリア人グイード・ダレッツッオという人が音に名前をつけたそうです。
その当時は音を人に伝えようとした時に歌って聞かせていたそうでして、どうにもやりづらく思ったのかグイード・ダレッツッオは音に名前をつけて人に伝わりやすくしたそうです。
なんでイタリア語
ドレミやピアノ、フォルテといった楽語はイタリア語が使われますが、なぜイタリア語が多いのでしょうか?
これは宗教と関係があるようで、イタリア・ローマがキリスト教カトリックの総本山だったことだとか、当時の音楽家は宮廷音楽家といったキリスト教に関する職についていたこととかが理由じゃないかと考えられているそうです。
音階の概念はピタゴラスが発見
音階の概念の法則はピタゴラスが発見したと言われています。
最初、 ピタゴラス??って驚きました。ピタゴラスといえばピタゴラスの定理が有名な数学者で、誰しも一度は聞いたことのある名前です。
どういう状況だったのか想像つかないんですけど、鍛冶屋さんがハンマーを振り下ろす音を聴いた時に、叩く鉄の長さによって違いがあることにピタゴラスは気がついたそうです。この長さの鉄とこの長さの鉄を同時に叩いたら、心地よく感じる音とそうでない音があることに気がついたそうです。
「万物は数である」という考え方を持っていたピタゴラスは、この協和する音を数学的に研究したんですね。
ピタゴラス音律とは
ピタゴラスは『ピタゴラス音律』という音階をつくり、最古の音律といわれています。 ウィキペディアによると、
音階全ての音と音程を周波数3:2の純正な完全五度の連続だら導出する音律である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ピタゴラス音律
となっています。 なんのこっちゃ分からないですよね?
ピタゴラスは弦の長さによる音と音の響きの心地よさの関係をピタゴラスは調べました。
ある長さの弦を弾いたとして、その弦の半分の長さの弦を弾くと1オクターブ上の音がするとか、3分の2の長さの弦を一緒に弾くと心地の良い響きがするという法則性を見つけていったんですね。
こうして音階を作っていったといわれています。
雑学ネタになる
音楽や数学に興味のなかった方でも知っているとトリビア的な知識になりそうです。 雑学として興味のある方は読んでみてください。飲み会の席で役に立つかも! それでは。