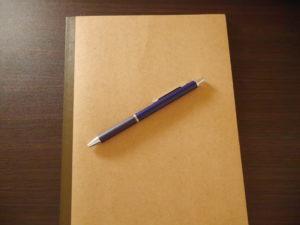ものを減らしたい!ミニマルに暮らしたい!でもどこから手を付けたら良いのか分からない…。
今回は、こんな悩みに自らの片付けの経験を踏まえてお話したいと思います!
部屋の片付けはどこから手をつけたらよいか?
結論として、
どこからでも良い!
というのが答えです。
考える前に片付けたいところからさっさと始めてしまえばよいと思うのですが、
手放しやすいアイテムで、なおかつアイテム数の多い場所
から優先的に始めるとよいと思います。
手放しやすいアイテムで、アイテム数の多い場所??
なお、ワンルームでしか片付け経験がないので、片付ける部屋はワンルームをイメージしてくださいね。
手放しやすいアイテムで数の多い場所から始める理由
手放しやすく、なおかつアイテム数が多い場所から始めるのを勧める理由は、
- 捨てる判断がしやすい
- 物の数をいっきに減らせる
- 達成感を得やすい
というのがあります。
捨てやすいアイテムで、なおかつ数が多い場所を優先的に片付けを行うことで、物の数を一気に減らすことができます。
そして、片付いた時のスッキリ感を得ることができます。
具体的にはこんな場所とアイテム
| 場所 | アイテム |
|---|---|
| 机まわり | 文房具、本、書面 |
| クローゼット | 衣類 |
| キッチン周り | 食器、調理器具 |
上記にあげた場所にあるアイテムは、本や衣類、食器などで、手放しても買い直しがしやすいものばかりです。失敗してもリスクが少ないでしょう。
そして、数や種類も多いと思うので、一気に物を減らすことができます。
もちろん、中には高価だったり、もう手に入らない物もあるかもしれません。
しかし、部屋の中でも散らかりやすい場所なので、一度片付けばとても快適になるでしょう。
実際にこの順番で行いました
机まわり➡️クローゼット➡️キッチンまわり
ちょっと記憶が曖昧ではありますが、自分がミニマリストになる過程でこの順番で片付けを行いました。
なんでこの順番だったかというと、
机まわり
部屋の中で一番長くいる場所。最初に落ち着ける空間にしたかった!
クローゼット
服は迷わず捨てやすい。片付いたあとのスッキリ感もある
キッチンまわり
まずは部屋の中をスッキリさせたく、優先度が低かった
というのが理由です。
ちなみに、こちらの記事に捨てたものをまとめています。
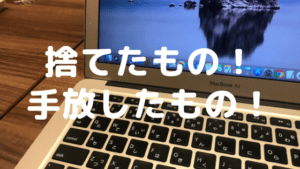
片付けの時に守っているルール
片付けのときに自分が守ってることは、
『一箇所終えてから、次の場所に取りかかる』
というルールです。
1箇所終えてから、次の場所に取りかかる
片付けをしていると、
他の場所が気になり出して、本来片付けたかった場所が片付けられなかった!
という経験はありませんか?
そうならない為にも片付ける順番をあらかじめ決めておくとよいでしょう。
1箇所を片付ける場所を決めたら、その次に片付ける場所をあらかじめ決めておきます。
片付ける場所と順番を決めておく理由
場所と順番を決めておく理由は、目標設定になるからです。
「今日は机まわりをやる!今度の土曜はクローゼットの中をやる!」
という具合に大雑把でもいいので、いつまでにどこを片付けるのか?という作業計画を決めておくとよいと思います。
作業計画を立てる理由
- 行動がブレづらい
- 目標の達成がしやすい
というのが計画を立てておく理由です。
片付ける場所の順番を決めておくと、思いつきで別の場所を片付け始めてしまうことを防いでくれます。
紙に書いておくと達成しやすい
具体的な目標設定は、やりぬく力を与えてくれると言われています。
また、紙に書くことで達成しやすくなるそうですよ。
「自分が望んでいるものは何か」これをはっきりとわかっている人は、そこに到達するまでやり抜くことができます。
具体的な目標を決めたら、そのために必要な行動は何かを具体的にすることも大切です。「いつまでに、何をするのか」を決めるのです。
『やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功科学』 著者 ハイディ・グラント・ハルバーソン
片付ける場所と順番を紙に貼り出しておきましょう。
目標達成の時に参考となる本はこちらです。
無理そうなら目標を細かくする
よし!まずは、机まわりから片付けはじめるぞ!
と意気込んでみたものの、
「あれ?予定通りに片付けを終えるのはむずかしそう!」
となってしまうことがあるかもしれません。
そんな時は、片付ける内容をさらに細かく分けます。
具体的にはこのように
- 本だけやる
- 書面だけやる
- 文房具だけやる
とこのように、いっぺんに無理に行おうとせず、達成しやすいように目標を小さく分けます。
目標を細分化することも、やり抜く力をを高めてくれるといわれています。
興味深いことに、「やり抜く力」の傾向予測手法で「やり抜く力」が低いと予測された人であっても、目標を細分化して小さい目標ごとに達成感が得られるような学習プログラムを用いると、最後までやり抜くことができました。
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
脳画像から「やり抜く力」を予測する手法を開発〜目標の細分化が脳を変化させ達成を支援〜
なるべく片付けの動きを止めない
片付けを行っていると、手放すか判断に迷うものも出てきます。
手放すかどうかで悩んで時間が過ぎてしまうものは、保留箱や仮置き場を用意しておくとよいです。
手放す判断に迷うもの
- 思い出の品
- 捨てると後で困るかもしれない書類
- たまに使うあった方が便利なもの
もちろん、判断に迷う思い出の品や写真は後回しでもよいと思います。
こういったものは、最後に手をつけるか一時的に保留し、なるべく作業の手を止めないようにしましょう。
物を所有するときの時の考え方
最後に、手放すルールとは反対にせっかく減らした物を増やさない為に、物を持つ時のルールや考え方についてです。普段から実行しています。
基本的に一つあれば十分な物は一つまで
よく言われていることですが、一つあれば十分なものは複数持たないことです。
例えば、ハサミや爪切りをなぜか2つ以上持っていることはありませんか?
一人暮らしなら基本的に1個あれば十分ですよね。
手放したことで不便にならないようにする
物を持つことは、基本的に管理する手間やコストがかかってしまいます。
だから、手放すことは=手間やコストを減らすことになります。
物を手放すことで快適になることを目指していると思います。
なので、物を減らし過ぎて不便になってしまっては本末転倒転倒です。
例えば、タオルとか、下着とか。
極限まで減らせば、一度に洗濯する量は減るかもしれません。
でも、逆に洗濯する回数が増えてしまったり、乾いてなくて次の日に着る物がない…!
なんてことになりかねません。
それに、電気代や水道代も増えちゃいそうですよね。
減らし過ぎて不便になるようならば、自分の中でうまく調整していくことも大事です!
極端に減らすと不便になるもの
- 下着やタオル
- 食材(買い物に行く手間が増える)
- 車、自転車などの移動手段
買う方が楽、手放すほうが大変の法則
これは捨てる技術というよりも、物を増やさないために知っておいた方がよいことです。
物を買って手に入れるのは、お店に行ったり、ネットでポチれば簡単にできてしまいます。配達もしてもらえるのでとても楽ですよね。
でも、「やっぱ合わなかったな、使わないな」といざ買ったものを手放そうとなったときに、とても面倒に感じませんか?
家具や家電なら粗大ゴミとして出したり、メルカリやリサイクルショップに持って行ったりと一苦労あるでしょう。
サブスクも入会するときは希望に満ちていて、でも使わなくなると解約が面倒でそのまま放置しちゃったりするんですよね…。
使わなくなったサブスク
- Adobeのフォトショップ
- スポーツジムの会員
何かを買う時は、捨てたり手放すときのことや、三日坊主に終わってしまう自分を少し想像してみると良いかもしれません。
 きっしー
きっしーちなみに3日坊主とは自分のことです…。笑
以前は衝動買いも多かったですが、手放す方が大変という法則を知ってから、無駄な買い物はあまりしないようになったと思います。
もちろん必要な物は買うし、ときには浪費もしますけどね。笑
無理せず少しづつで
というわけで、今回は自分が実際に行った片付けの順番や考え方についてでした。
いっぺんにやろうとすると挫折すると思うので、計画をたてて、無理ない範囲で少しづつ行うのが良いと思いますよ。
よかったらこちらの記事も読んでみてくださいね。
それでは!